銀マニ?▶マニア登録!▶マイページ
銀河星雲マニアのバイブル誕生!

 Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト!
Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト!
 企画:JUNPY
企画:JUNPY



ランキング!▼▲
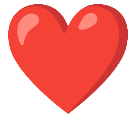 いいね数獲得ランキング いいね数獲得ランキング |
| 総合部門 | | 1 |  だっちぇす だっちぇす
(神奈川県 since 2020) | 21
いいね | | 2 |  永遠銀河 永遠銀河
(熊本県 since 2022) | 21
いいね | | 3 |  JUNPY JUNPY
(福岡県 since 2021) | 8
いいね | | 4 |  ほしたろう ほしたろう
(兵庫県 since 2014) | 7
いいね | | 5 |  めだか めだか
(千葉県 since 2023) | 7
いいね |
 初心者部門 初心者部門 | | 1 |  永遠銀河 永遠銀河
(熊本県 since 2022) | 21
いいね | | 2 |  JUNPY JUNPY
(福岡県 since 2021) | 8
いいね | | 3 |  めだか めだか
(千葉県 since 2023) | 7
いいね | | 4 |  だらしん だらしん
(新潟県 since 2025) | 2
いいね | | 5 | | |
|
 撮影天体数ランキング 撮影天体数ランキング |
| 総合部門 | | 1 |  だっちぇす だっちぇす
(神奈川県 since 2020) | 18
天体 | | 2 |  星好きスズメ 星好きスズメ
(兵庫県 since 1970) | 12
天体 | | 3 |  JUNPY JUNPY
(福岡県 since 2021) | 11
天体 | | 4 |  永遠銀河 永遠銀河
(熊本県 since 2022) | 10
天体 | | 5 |  たつまる たつまる
(栃木県 since 2020) | 8
天体 |
 初心者部門 初心者部門 | | 1 |  JUNPY JUNPY
(福岡県 since 2021) | 11
天体 | | 2 |  永遠銀河 永遠銀河
(熊本県 since 2022) | 10
天体 | | 3 |  めだか めだか
(東京都 since 2023) | 6
天体 | | 4 |  だらしん だらしん
(新潟県 since 2025) | 2
天体 | | 5 | | |
|
オリオン大星雲
M42


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/2.html#148

 だらしん ▶
だらしん ▶
(新潟県 since 2025)■天体望遠鏡:SVBONY SV503
■カメラ:ASI585 MC Air
■フィルター:4
■撮影場所:茨城県かすみがうら市
■この天体の攻略難易度:4
■私の攻略法:光害の影響が少ない南中前後に撮る
■赤道儀:VIXEN SX2
■オートガイド:ASIAIR
■画像編集ソフト:Siril+LightRoom
■撮影日時:2026/2/12
■ゲイン:252
■露光:「120秒 × 63枚」
<■加工前写真の説明>
スタック用のソフトをASIのDeepStackからフリーソフトのDeepSkyStackerにかえたところ、オリオン座付近にたくさん飛んでいる人工衛星の軌跡が綺麗に消えてくれました。
<■撮影や編集の過程説明>
最近SirilにVeraLuxという一連のスクリプトが追加されて、カブリ補正やデノイズ、カラーグレーディングなどの処理が高品質に行えるようになりました。これらのスクリプトを一つ一つ機能を試しながら使ってみました。CosmicClarityを使ってシャープネスも高めています。
<■ノーハウ・秘訣>
周辺の分子雲は、敢えてあまりあぶり出さないようにしてみました。
SV50380EDは、お手頃価格なのに星像がとてもシャープです。
つづき▼▲大きなセンサーのカメラを使わなければ、これで充分な気がします。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/2.html#148
アンドロメダ銀河
M31


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/33.html#147

 だらしん ▶
だらしん ▶
(新潟県 since 2025)■天体望遠鏡:Askar FMA180
■カメラ:ASI585 MC Air
■フィルター:なし
■撮影場所:茨城県かすみがうら市
■この天体の攻略難易度:7
■私の攻略法:天頂近くにいるときに暗い場所で撮影する
■天体望遠鏡:AskarFMA180
■赤道儀:AZ-GTi(赤道儀化)
■オートガイド:ASIAIR
■画像編集ソフト:Siril + GraXpert + Lightroom
■撮影日時:2025/11/15
■ゲイン:200
■露光:「180秒 × 40枚」
<■加工前写真の説明>
FITSの撮って出しをjpgに変換しました。
<■撮影や編集の過程説明>
Seestarでの撮影からステップアップしたくなり、機材をそろえてアンドロメダ銀河に挑戦してみました。10月にも1度撮影してみたのですが、月が出ていたためにカブリを軽減しようとCLSフィルターを装着したところ、露光が不足したのか淡い像しか得られず。今回は空の暗い場所に遠征し、月が昇る前に天頂のアンドロメダをフィルターなしで撮影しました。
<■ノーハウ・秘訣>
超若葉マークなので機材を正常に作動させるのでいっぱいいっぱいでした。ASIAIRのガイドが古いキャリブレーション値を再利用していたため、どんどんガイドがずれて撮影にならず、問題解決まで2時間ロスしました(涙)
図鑑で見るような姿のアンドロメダ銀河が、自分のPCの画面に表示された瞬間は感無量でした。
つづき▼▲
次は寒さ対策をしっかりしてオリオン星雲に挑戦してみます。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/33.html#147
さんかく座銀河
M33


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#146

 たつまる ▶
たつまる ▶
(栃木県 since 2020)■天体望遠鏡:SVBONY SV550APO 80mm
■カメラ:Canon EOS 60D
■フィルター:なし
■撮影場所:栃木県鹿沼市
■この天体の攻略難易度:8
■私の攻略法:思い切ってトリミングする。
■赤道儀:EQ5GOTO
■オートガイド:SS-oneオートガイダーPRO
■画像編集ソフト:Pixinsight Photoshop
■撮影日時:2024/11/10
■ゲイン:ISO1600
■露光:4分×29枚
<■撮影や編集の過程説明>
馬頭星雲が十分高くなるまでの暇つぶしで撮影しました。
星雲とは違い、モクモクではなく銀河の腕が分かるように処理しました。
<■ノーハウ・秘訣>
撮影自体は特に工夫はありません。
温度変化でピントが狂うので、1時間程度でピント合わせ直してました。
BXTで恒星の大きさが小さくなりすぎると寂しい感じだったので、恒星だけストレッチを強めにかけています。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#146
馬頭星雲
IC434


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/7.html#145

 たつまる ▶
たつまる ▶
(栃木県 since 2020)■天体望遠鏡:SVBONY SV550APO 80mm
■カメラ:Canon EOS 60D
■フィルター:なし
■撮影場所:栃木県鹿沼市
■この天体の攻略難易度:6
■私の攻略法:明るい星の周りにゴースト(変な反射の円盤)が出てしまい苦労しています。今度撮影する機会があれば、UV/IRカットフィルターを入れて、余計な波長が入り込まないようにしてみます。
■赤道儀:EQ5 GOTO
■オートガイド:SS-oneオートガイダーPRO
■画像編集ソフト:Pixinsight Photoshop
■撮影日時:2024/11/10
■ゲイン:ISO1600
■露光:5分×35枚
<■撮影や編集の過程説明>
撮影自体は特に工夫はなく、明るい部分が白飛びしない程度に露光時間を決めて、あとは放置でした。
赤いモヤモヤが多い領域なので、ニュートラルをどこにするかが難しいと感じています。
あと、冬は寒いので撮影自体がしんどいです。
<■ノーハウ・秘訣>
出来るだけ放置で車の中にいるようにしました。
つづき▼▲
ポータブルガスストーブを持って行って、暖をとれるようにしました。
薄いモヤモヤを描出することに拘らず、あまり画像が荒れない範囲での画像処理に留めました。
明るい星のゴーストをどうやってやっつけるか悩んでいます。
ガイドがどうしても上手くいかないので、システムの見直しを考えています。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/7.html#145
わし星雲
M16


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/31.html#144
 古希 ▶
古希 ▶
(埼玉県 since 1970)■天体望遠鏡:TAKAHASHIscope
■カメラ:ZWOASI294MCPro
■フィルター:sightron
■撮影場所:埼玉県秩父市
■この天体の攻略難易度:8
■私の攻略法:雲の無い日を選ぶ
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/31.html#144
亜鈴状星雲
M27


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/23.html#143
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/23.html#143
ひまわり銀河
M63


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#142
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#142
さんかく座銀河
M33


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#141
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#141
アンドロメダ銀河
M31


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/33.html#140
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/33.html#140
三裂星雲
M20


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/27.html#139
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/27.html#139
ひまわり銀河
M63


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#138
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#138
亜鈴状星雲
M27


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/23.html#137
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/23.html#137
ボーデ銀河
M81


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/19.html#136
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/19.html#136
黒眼銀河
M64


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/14.html#135
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/14.html#135
ソンブレロ銀河
M104


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/16.html#134
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/16.html#134
ひまわり銀河
M63


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#133
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/17.html#133
子持ち銀河
M51


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/15.html#132
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/15.html#132
オリオン大星雲
M42


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/2.html#131
 星好きスズメ ▶
星好きスズメ ▶
(兵庫県 since 1970)■天体望遠鏡:Vespera
■撮影場所:明石川
■この天体の攻略難易度:1
■撮影日時:2023/10/29
■ゲイン:20db
■露光:「秒 × 枚」+「秒 × 枚」
10s×5 50秒
<■加工前写真の説明>
加工無し
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/2.html#131
干潟星雲
M8


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/25.html#130
 星好きスズメ ▶
星好きスズメ ▶
(兵庫県 since 1970)■天体望遠鏡:Vespera Ⅰ
■撮影場所:明石川
■この天体の攻略難易度:1
■私の攻略法:初めてなので望遠鏡まかせ
■撮影日時:2023/09/29 19:52-19:55
■ゲイン:20db
■露光:10s×11
<■加工前写真の説明>
撮って出し
<■撮影や編集の過程説明>
初めてなので別に無し そのまま
<■ノーハウ・秘訣>
別になし
神戸西神中央駅近辺の明かりが見えるなかで電視観望出来た証拠なのでこの短い時間でこれだけ撮れたら言う事無し。これからいろいろ試したい
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/25.html#130
馬頭星雲
IC434


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/7.html#129

 JUNPY ▶
JUNPY ▶
(福岡県 since 2021)■天体望遠鏡:FS-60CB
■カメラ:ASI183MC
■フィルター:SVBONY UV IRカットブロックフィルター
■撮影場所:小石川原ダム(福岡)
■この天体の攻略難易度:5
■私の攻略法:フィルターをつけないで撮影
■赤道儀:AZ-GTi
■オートガイド:ASIAIAR
■画像編集ソフト:Affinity Photo 2
■露光:「120秒 × 10枚」
「何故、自分の燃える木は赤い?」
この疑問をたつまるさん
コチラに質問したところ・・・
「QBPフィルターを使うと、燃える木が白っぽく写りません」
とのことで、フィルターをハズして写したところ・・・あっさり黄色く写った(笑)
フィルターのつけっぱなしはよくないのねー

リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/7.html#129
ソンブレロ銀河
M104


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/16.html#128

 JUNPY ▶
JUNPY ▶
(福岡県 since 2021)■天体望遠鏡:FS-60CB
■カメラ:ASI183MC
■フィルター:SVBONY UV IRカットブロックフィルター
■撮影場所:草千里展望所(熊本県阿蘇市)
■この天体の攻略難易度:5
■赤道儀:AZ-GTI
■オートガイド:ASIAIR
■画像編集ソフト:Affinity Photo 2
はじめて見た時から、その壮大な姿に圧倒されっぱなしのハッブル宇宙望遠鏡撮影の「ソンブレロ銀河」。

が、自分で撮影したものからは、その壮大さが伝わってこなかった。

ハッブル撮影のものと何が違うのかを考えた時
●中心部の白さ
●暗黒帯の色
だと思った。
そこで、暗い場所(草千里展望所)で撮影したところ、暗黒帯がハッブルと同じ色(茶色)になったので、画像処理で中心部を白っぽくしたところ、まあまあ近くなったかな、と(^_^;)
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/16.html#128
雷神の兜星雲
NGC2359


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/12.html#127

 JUNPY ▶
JUNPY ▶
(福岡県 since 2021)■天体望遠鏡:FS-60CB
■カメラ:ASI183MC
■フィルター:sightron
■撮影場所:草千里展望所(熊本県阿蘇市)
■この天体の攻略難易度:5
■赤道儀:AZ-GTi
■オートガイド:ASIAIR
■画像編集ソフト:Affinity Photo 2
■露光:「120秒 × 10枚」
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/12.html#127
パックマン星雲
NGC281


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/38.html#126

 JUNPY ▶
JUNPY ▶
(福岡県 since 2021)■天体望遠鏡:FS-60CB
■カメラ:ASI183MC
■フィルター:SVBONY UV IRカットブロックフィルター
■撮影場所:自宅ルーフバルコニー
■この天体の攻略難易度:5
■赤道儀:AZ-GTi
■オートガイド:ASIAIR Plus
■画像編集ソフト:Affinity Photo 2
■露光:「120秒 × 10枚」
パックマンの黄色に寄せて画像処理。

リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/38.html#126
さんかく座銀河
M33


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#125

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ 1057mm
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:CBPフィルター
■撮影場所:産山
■この天体の攻略難易度:1
■私の攻略法:前回はライブスタックだったので取り直しCBPフィルターで淡いガスを撮影してみました。
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:FMA180+ASI120MM
■画像編集ソフト:ステライメージ9+Photoshop
■撮影日時:12月13日
■ゲイン:100 -10℃
■露光:「120秒 × 59枚」
<■加工前写真の説明>
揺らいでいる画像を外してコンポジット
<■撮影や編集の過程説明>
photoshopのマスクを活用して何度もレベル調整して星雲を強調してみました。
<■ノーハウ・秘訣>
やはり暗い場所で弱いフィルターで撮影すると綺麗に出ますね。さんかく座の中にある散光星雲であるNGC604もある程度映ってくれていました。
たくさんある散光星雲が綺麗さを引き立ててくれています。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#125
かに星雲
M1


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/3.html#124

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ 1057mm
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:CBPフィルター
■撮影場所:産山
■この天体の攻略難易度:2
■私の攻略法:焦点距離の長い望遠鏡
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:FMA180+ASI120MM
■画像編集ソフト:ステライメージ9+Photoshop
■撮影日時:12月13日
■ゲイン:100
■露光:「120秒 × 19枚」
<■加工前写真の説明>
焦点距離が1057㎜でも小さいかに星雲は淡い
<■撮影や編集の過程説明>
内部構造やパルサーが見えるように処理してみました
<■ノーハウ・秘訣>
風が強かったため露光時間を短くして撮影
焦点距離が長い鏡筒で撮影すると、フィラメント構造がはっきりと出ました。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/3.html#124
クラゲ星雲
IC443


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/5.html#123

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:OPTOLONG L-Ultimet
■撮影場所:産山
■この天体の攻略難易度:7
■私の攻略法:まだ攻略できていません。
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:FMA180+ASI120MM
■画像編集ソフト:ステライメージ9+Photoshop
■撮影日時:12月7日
■ゲイン:100 -10℃
■露光:「300秒 × 58枚」
<■加工前写真の説明>
1時ごろに月が上がってくるため、カブリ対策でUltimetを選択、しかし明るい恒星にハロが出てしまいました。
<■撮影や編集の過程説明>
編集でハロを小さくする方法が分からず、強調するとハロが強調され飽和してしまいました。マスク処理も試しましたが画像編集初心者には難しく課題が残る編集となってしまいました。
<■ノーハウ・秘訣>
クラゲ頭のガスが濃い部分や、足部分のOⅢを出したくて最強フィルターを使い出す事は出来ましたが、課題が残り時開はハロが出ない方法を考えたいと思います。
星雲の濃さや星雲の中の模様が複雑でもっと時間をかけて撮影したく思いました。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/5.html#123
プレアデス星団
M45


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/9.html#122

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:CBPフィルター
■撮影場所:産山
■この天体の攻略難易度:3
■私の攻略法:CBPフィルターで淡いガスを撮影してみました。
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:FMA180+ASI120MM
■画像編集ソフト:SI9+Photoshop
■撮影日時:12月7日
■ゲイン:100
■露光:「300秒 × 30枚」
<■加工前写真の説明>
30枚コンポジットでSI9で青い星雲は出てきました
<■撮影や編集の過程説明>
M45はナローバンドでは映りにくいためCBPフィルターで狙ってみました。CBPフィルターなので月によるカブリが嫌だったので月が出る前の時間で撮影してみました。
ただ、photoshop編集は初心者で難しく、今回初めて星マスクを勉強しながら作りましたが、まだまだ練習が必要です。
<■ノーハウ・秘訣>
フィルター使い分けでしょうね
焦点距離が長い鏡筒なので、次回は400㎜の望遠鏡でプレアデス星団周りのガスを出してみたいと思います。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/9.html#122
ばら星雲
NGC2237


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/8.html#121

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:OPTOLONG L-Ultimet
■撮影場所:ひごたい公園
■この天体の攻略難易度:3
■私の攻略法:暗黒星雲を十分出すために長時間の撮影
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:FRA180+ASI120MM
■画像編集ソフト:ステライメージ9+Photoshop
■撮影日時:12月3日
■ゲイン:300
■露光:「300秒 × 39枚」
<■加工前写真の説明>
ステライメージでコンポジットしただけである程度滑らかな画像になりましたが、色々あって半分以上使えず、さらに雲で中心から少しずれてしまいました。
<■撮影や編集の過程説明>
途中で分厚い雲が出て、時間がもったいないのでダーク撮影を行い、完了後に晴れている時間ごろからLIGHT撮影予約をして仮眠、起きて確認すると少し中心からずれてしまっていました。残念。
<■ノーハウ・秘訣>
闇夜でフィルター
星雲全部赤だと思っていたら、中心部は薄い赤で次回は中央にもっと長時間撮影をトライします。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/8.html#121
さんかく座銀河
M33


リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#120

 永遠銀河 ▶
永遠銀河 ▶
(熊本県 since 2022)■天体望遠鏡:Askar151PHQ
■カメラ:ASI2600MC PRO
■フィルター:CBPフィルター
■撮影場所:星野村
■この天体の攻略難易度:3
■私の攻略法:電視観望なので攻略法はありません、あえて言うならCBPフィルターかな
■赤道儀:ZWO AM5
■オートガイド:ヤフオクぽちっ
■画像編集ソフト:Sharpcap
■撮影日時:11月2日
■ゲイン:200
■露光:「30秒 × 10枚」
<■加工前写真の説明>
九州の星野村で開催された天文ハウストミタさんの星宴でSharpcapを使った電視観望時の画像です。たくさんの方に良く映ってますねと言われて嬉しかったです。
<■撮影や編集の過程説明>
IR/UVカットフィルターだと色が出ず、星雲用のフィルターだと映らなくて、CBPフィルターを買って使ったところ、さんかく座銀河にある星雲まで移す事が出来ました。
<■ノーハウ・秘訣>
フィルターの重要性と選定
他の銀河にある星雲が見えるとロマンがさらに広がります。
リンクURL
https://t.maniaxs.com/gzukan/i/2022/37.html#120



 Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト!
Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト! 企画:JUNPY
企画:JUNPY



 Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト!
Seestar専用ニュース&コミュニティーサイト! 企画:JUNPY
企画:JUNPY
